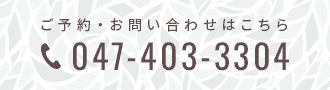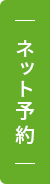今までにこのブログでは、
鍵盤楽器を中心に、さまざまな楽器を紹介してきました。
今回は、「アルモニカ」という珍しい楽器を取り上げます。
別名は、グラス・アルモニカ、グラス・ハーモニカ。
元々は、グラス・ハープを起源としています。
その音色と響きは、他に類をみず、
涼しげな音は、酷暑に悩むこの時期に、
一服の清涼剤となることでしょう♪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%
<グラス・ハープ>
ガラス製の水を入れたグラスの縁を擦って音を出す楽器です。
口径・腰径の異なる複数のグラスを大きさ順、
12平均率音階に並べて、水で濡らした指先を
ガラスの縁に触れさせる摩擦によって、
共鳴するガラスから音を出す仕組みです。

紀元前2300年前には、存在していたとされ、
ルネッサンス期より前に、
音が鳴る仕組みについて文書化されています。
アイルランドの音楽家リチャード・ポックリッジは、
この楽器を現在のように奏した最初のものとみなされています。
彼は1742年から、様々な量の水を入れて並べられたグラスのセットを、
ロンドンで演奏していたことが知られています。
ただ、指から滴り落ちる水や、
水の蒸発などによって音程が狂いやすく、
事前に水を入れて調律する必要があり、
準備が大変というのが難点でした。
作曲家クリストフ・ヴィリバルト・グルックは、
1746年に「泉水で調律された26の音楽用グラスによる」
と銘打った演奏会を開催しました。
18世紀頃には広く楽器として演奏されるようになり、
1761年にグラス・ハープを改良した
アルモニカが発明されたことによって
ヨーロッパ中で大流行します。
☆バッハ:Suite BWV.996 Bourrée
元々はリュートのために作曲されたと考えられている曲を
グラス・ハープで。
調性は違いますが、原曲の澄んだ音を
上手く変換していると思います。
原曲をリュートで。
☆Pachelbel:Canon in D major
パッヘルベルの「カノン」をグラス・ハープの多重録音で。
バイオリンで聴く元曲ももちろん良いのですが、
響き渡るグラス・ハープの音が、荘厳で、
まるで教会の中で聴いているような気分になります。
✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎
<アルモニカ>
アルモニカは、グラス・ハープを工夫し、
多数の音を様々に奏しやすくさせ、細かな音の動きや、
同時に多数の音を独りで奏することが容易になりました。
発明したのは、雷が電気であることを発見したり
避雷針の発明で有名な、ベンジャミン・フランクリン。
直径の異なる碗状にした複数のガラスを
大きさ順に十二平均律の半音階に並べ、
それらを鉄製などの回転棒に突き刺して回転させながら、
水で濡らした指先をガラスの縁に触れさせる摩擦によって、
グラス・ハープと同様に共鳴するガラスからの音で音楽を奏でます。
(わかりにくいので、この記事では、
グラス・ハープを、グラスを並べたもの、
グラス・アルモニカ、アルモニカを、
円錐形のガラスを回したものとします)

☆Sugar Plum Fairy by Tchaikovsky
金平糖の精の踊り(チャイコフスキー「くるみ割り人形」より)
グラス・ハープのデュオで。
ガラスというより金属音に近いような音色。
他のグラスにも振動が伝わるため、
出そうとしている音以上に、共鳴音が響きます。
グラス・アルモニカ、ハープ、クラリネットによる演奏。
グラス・ハープよりも柔らかい音色。
音の余韻をコントロールできるので、
より深みのある演奏になっています。
☆モーツァルト:アダージョとロンド ハ短調 K.617
楽器編成はグラス・アルモニカ、フルート、
オーボエ、ヴィオラ、チェロの五重奏。
モーツァルトが、盲目のグラス・アルモニカの名手
マリアンネ・キルヒゲスナーのために
1791年5月23日に作曲し、
6月10日、ウィーンの音楽アカデミーで初演されました。
続いて、8月19日にケルントナートーア劇場でも演奏されています。
アルモニカの音が、残響に支配されるため、
音が重ならないように聞かせようとするためか、
比較的ゆったりとしたテンポで演奏されています。
特にソロの部分では、それが際立っています。
同じ編成の演奏。
一音一音の粒立ちははっきりしないけれど、
躍動感がある演奏。ただ、より金属音に近く好みの分かれるところ。
初演時のアンコールのために、ソロ用に作曲されたとされるのが、
☆Wolfgang Amadeus Mozart :Adagio for Glass Harmonica, K 356
Glass Harmonica:Dennis James
同じ調性のこの曲は、ゆったりとしていて、
アルモニカの響きを重視した作品。
✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎
<アルモニカの楽曲>
この魅惑的な音色を持つ新しい楽器は、
最初から熱狂的な支持を得て、
人々はその音色に酔いしれ、練習に熱中し、
1700年代のうちにおよそ4,000〜5,000台ほどの台数が、
欧州各地に出回ったとされています。
また、楽器に関する多数の著作物が生み出され、
この楽器のために、400にものぼる作品が作曲されました。
その中には、モーツァルト、ベートーヴェン、
リヒャルト・シュトラウス、ドニゼッティ、サン=サーンスなど、
現代の我々にとって親しみ深い
大作曲家たちによる作品も含まれています。
ベートーヴェン作曲の
舞台劇《レオノーレ・プロハスカ》のための音楽
WoO.96 (Leonore Prohaska)、
第3曲「花輪にくるまれたあなた」は、
グラス・アルモニカにナレーションという構成です。
サン=サーンスの「動物の謝肉祭」は、
楽器の構成に”Harmonica”とあります。
(グラス・アルモニカを指すとされるが、
稀少楽器であるため、チェレスタや
グロッケンシュピールで代用することが多い)。
☆サン=サーンス:「動物の謝肉祭」
第7曲「水族館」(Aquarium)
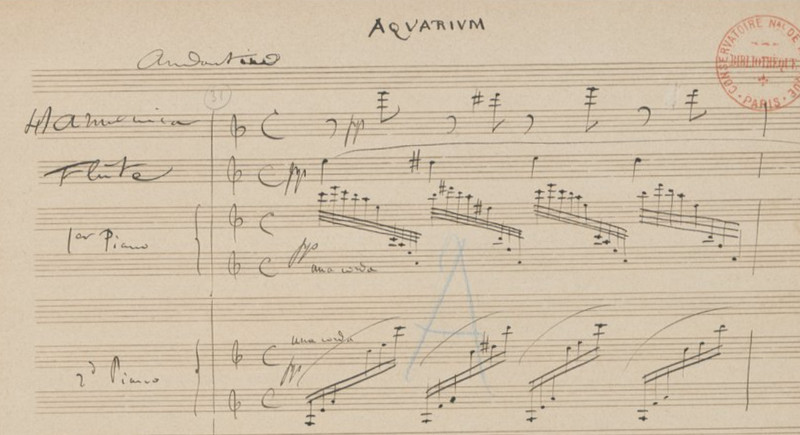
幻想的なメロディーに、
分散和音のピアノ伴奏が添えられている。
フルート、アルモニカ(グラス・ハープ)、
ピアノ2、ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ、チェレスタ。
残念ながら、アルモニカを使用した演奏や録音は、
ほとんどありません。
それは、アルモニカ自体楽器が少なく、演奏者もいない事、
ホールが大きくなり、オーケストラの編成も大きくなって、
デリケートなアルモニカとバランスが取れなくなった事によります。
この録音は、非常に珍しいグラス・ハープを使用したもの。
チャールズ・グローヴズ指揮/フィルハーモニア管弦楽団
サン=サーンスが、アルモニカの音色を聞き、
その音の響きをイメージして、
この曲を書いたのは間違いないでしょう。
代替楽器で演奏したものとは全く違う印象。
水槽の中の水が、魚の動きと、
上からの光を浴びてキラキラと煌めく様を、
グラス・ハープの音が見事に表しています。
中盤に代替楽器が演奏する部分もありますが、
後半の共鳴音は、明らかにグラス・ハープのそれ。
さらに、第14曲「終曲」(Final)にも、
アルモニカの記載があります。
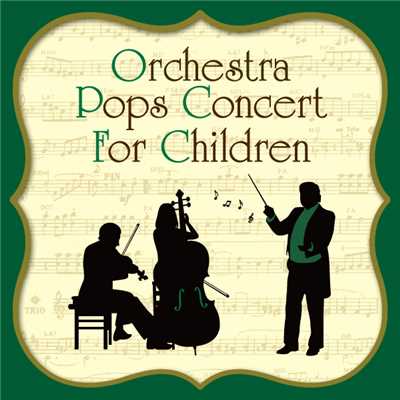
「動物の謝肉祭」は、
チェロが演奏する「白鳥」が何と言っても有名。
稀にみる才能を持った音楽家であり、
超絶ひねくれ者だったサン=サーンスが生み出した傑作。
全曲を聴いたことがない方には、
構成する曲のタイトルの意味や背景、
さらにその先の彼らしい皮肉やパロディを含めて、
是非通して聴いて頂きたい曲です♪
(水族館 8:27~)
この動画では、ほんの少しではありますが、
アルモニカを実演で使用しています。
(この曲についての詳しい解説は、機会を見てまた是非)
☆ヨハン・アブラハム・ペーター・シュルツ :ラルゴ 0:00〜
☆Johann Julius Sontag von Holt Sombach :アダージョ 8:07〜
トマ・ボロッホ(Thomas Bloch)は、オンド・マルトノ、
グラス・アルモニカ、クリスタル・バシェットなどの
珍しい楽器を専門とするクラシック音楽家。
パリ国立高等音楽院でオンド・マルトノの最優秀賞を受賞しています。
そんな彼の演奏から、シュルツの「ラルゴ」とSombachの「アダージョ」を。
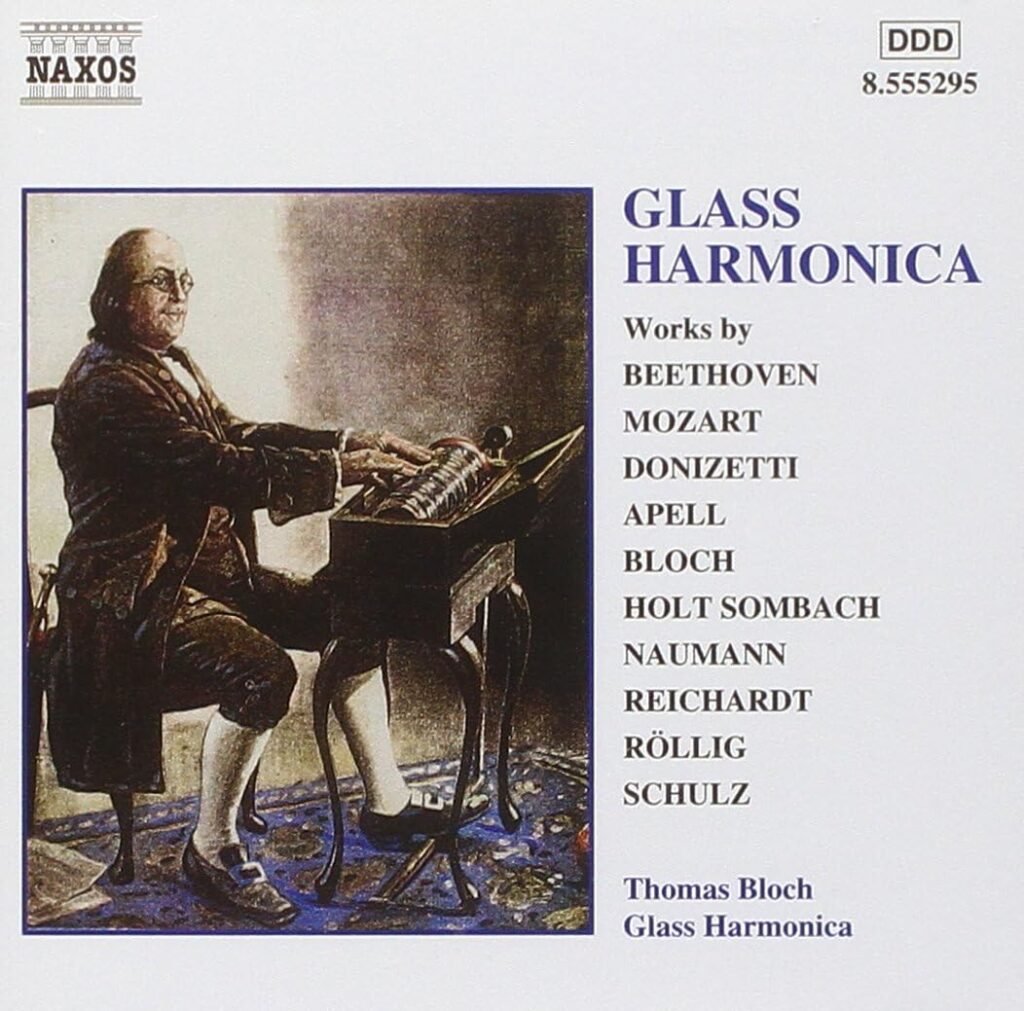
☆ヨハン・フリ-ドリヒ・ライヒャルト :ロンド 変ロ長調
ライヒャルト(1752〜1814)は、生涯旅に明け暮れた音楽家。
この曲は、グラス・アルモニカと
コントラバスをメインにした弦楽四重奏による。
高音のよく響くアルモニカと、低音のコントラバスの対比が面白い。
その間を絶妙にバイオリンとビオラが取り持っています。
音楽の流行が壮大なものに変化してしまったことに起因し、
この楽器は、人々の目からほぼ完全に姿を消してしまいました。
少なくとも公の演奏では、
どこにおいても見かけることはできなくなりました。
✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎
こうして衰退してしまったこのアルモニカですが、
熟練したガラス吹き師であり音楽家である
ゲアハルト・B・フィンケンバイナー(Gerhard B. Finkenbeiner)によって
1984年に復興されます。
☆Pachelbel:Canon in D major
Dean Shostakによるグラス・アルモニカによる演奏で。
先述したグラス・ハープの演奏と違い、
音数が多く、ハーモニーが曲全体に行き渡る。
五指を自由に使え、下の音程から、
高さが順番に並んでいるからこそ出来る演奏。
✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎
<日本におけるグラス・アルモニカ>
ガラスの専門家である小塚三喜夫が日本における第一人者です。
2000年4月には、フィラデルフィアで開催された
「グラス・ミュージック・フェスティヴァル」に招聘され、
海外の舞台でこの楽器を奏した最初の日本人として、
日本におけるこの楽器の歴史を道づけました。
小塚は、尾西秀勝とともに、
日本における復興活動に献身しており、
アルモニカのための貴重な演奏が広がりつつあります。
尾西は、2007年に国内で唯一のアルモニカ奏者として演奏を開始。
2008年サン=サーンスの「動物の謝肉祭」を
チェロ他と共にアルモニカで演奏。
日本人の演奏として世界初演となりました。
他にも、モーツァルトの「アダージョとロンド ハ短調 K.617」など、
それまで日本で(本来の楽器によって)演奏するには、
海外から奏者を招かなければ無理であった幻の作品群が、
次々と舞台で紹介され、各界で大きく期待されています。
尾西は作曲家であることから、
この楽器を用いた編曲や企画を展開していて、
この楽器の魅力が、独創的な形で日本に紹介されつつあります。
音楽雑誌やTV番組に多く出演し、
密かに始まりつつあるこの貴重な楽器のブームの
火付け役となっています。
椎名林檎の楽曲「駆け落ち者」に、
尾西のアルモニカ演奏が使用されています。
✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎
1952年フランスの音響彫刻家ベルナール・バシェ、
フランソワ・バシェの兄弟が、
グラス・ハープの現代版とも言うべき楽器を新たに考案します。
それが「クリスタル・オルガン(クリスタル・バシェ)」。
54本の金属管が鍵盤状に並んだガラス棒に連結され、
ガラス棒を指で触れると金属管がオルガンのパイプのように
共鳴して音が出るという音響彫刻の一種。
グラス・ハープやアルモニカより
音量が大きく音域も広い、といった特徴があります。
クリスタル・オルガンもさまざまな作曲家が作品を書いたり、
『皇帝ペンギン(2005)』、『ソラリス(2002)』といった映画音楽にも
効果的に使用されたりしています。
武満徹もこの楽器を使った楽曲を書いています。
☆バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番ト長調 BWV.1007
ガラス棒の振動が加わることで、
アルモニカよりも、倍音の共鳴が明らか。
☆Erik Satie : Gnossienne No.1
2台のクリスタル・バシェによる演奏。
サティの曲が持つ独特の浮遊感が上手く表現されている。
☆Dreamland : Cristal Baschet & Ayasa Handpan
Karinn Helbert & Jeremy Nattagh
クリスタル・バシェと、オランダ生まれのアヤサという
スティールパン(の一種)のデュオ。
金属の響きと共鳴するクリスタル・バシェの音が心地よい。
✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎
ガラスという他に類を見ない特異な素材を使った楽器の魅力を
少しは紹介できたと思いますが、いかがでしたでしょうか?
この楽器の、涼やかで神秘的な音で、
暑さを緩和出来たなら、ありがた山の寒烏(ガラス)。
「べらぼう」風でしめてみました
お後がよろしい様で。
カノンデンタルクリニック
〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-23-1 雷門ビル2F
TEL:047-403-3304
URL:https://www.canon-dc.jp/
Googleマップ:https://g.page/r/CTHgLGNJGZUXEAE